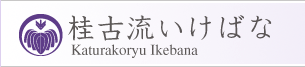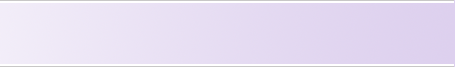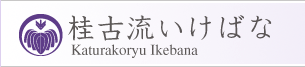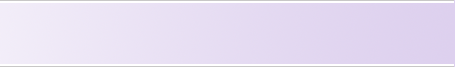|
第二百十三回: 活け花の残し方、進め方
今、日本は大きな節目を迎えている。戦後日本のシステムとの決別である。戦後のベビーブームで誕生した人が後期高齢者となられ、仕事の第一線から退かれた。当時流行っていた商品も変換を求められる時代となった。
自動車はハイブリット又は電気自動車となり、ガソリンから離れようとしている。マスメディアもコンプライアンスやハラスメントの枠組みの中で、非常に厳しい番組制作をしている。芸能人も同じ理由で職種を変えるもの、有料番組や劇場のみの活動する道を選ぶ。流通も教育も、果ては恋愛までオンラインが幅をきかせ始めている。
私達はターザンが蔓から蔓へ飛び移るように、次の社会がどのような形状になるか注視しながら、飛び移らなくてはならない。その一方で活け花は何を残していくべきか悩む時機である。
今、人気の鉄道に大井川鐵道がある。人々の目当当は蒸気機関車である。電車と 比べて蒸気機関車の魅力は、走っている燃料が石炭と分かる点もある。
機関士が一生懸命に石炭をくべ、燃えたぎる熱を蒸気として走るという 原理は、細かい事は余からなくても理解できる。ご飯を食べて一生懸命働いているように見える。「頑張れー!」と応援したくなる。
大井川鐵道のSLはC11型と C10型をメインに運行している。C11型は戦前の昭和17年(会長と同じ年である!) に製造された。資料も古く、言葉も現代で使われない用語だったりする。
内容が理解できても、肝腎の部品がない。仕方ないので手作りで交換している。
これを知って、非常に活け花的な発想だと感じた。私達も先代から完全な形で受け継げる訳ではない。知識や技術の継承できなかった部分は、資料から予想したり、幹部や時には他流の先生からも尋ねたりしながら「恐らくこのような形であったろう」と言う程度の分野もある。
かつて華道古書集成という本を手に入れたが全く読めない。当時のいけばな評論家の第一人者だった工藤昌伸先生に甘えながら「先生、全訳とかお持ちですか?」と尋ねると「字があるだけ有り難いと思いなさい」と穏やかに、しかし手厳しく嗜められたのを思い出す。
さらに大井川鐵道の凄いところは、蒸気機関車を昔のまま走らせるのではなく、機関車トーマスを走らせている点だ。本物のトーマスが目の前にくれば大人も夢中になる。我を忘れて写真を撮っているらしい。我々が次の時代に物を残すには、多くの人に興味を持ってもらわなくてはならない。今まで無関心だった人を振り向かせなくてはならない。
歌舞伎は裾野を広げる事に、必死になっている伝統芸能だろう。新作歌舞伎、スーパー歌舞伎を通じ、現代のアニメやゲームまでも歌舞伎に取り込んでしまおうと貪欲な革新に溢れている。その先頭にいつも人気役者が立っている。彼らは常に流行の先端に目を光らせ、旬な話題に食い込む機会を狙っている。
我々いけばなはどうか。今まで興味のなかった人々を巻き込むには周りが「眉をひそめる」ような変化も時に必要なのに、避けていないか。穏便に「昨年通り」を繰り返していないか。
実力があれば、定型から離れる事も時には必要となる。守破離の破、そして離の段階になる。
六世家元先代華盛が、驚くような花材で見事な立活けを形にしていた。その心意気を忘れずにいたい。
|