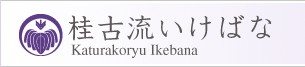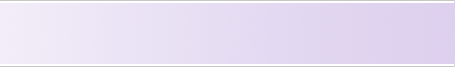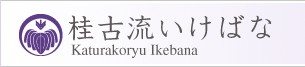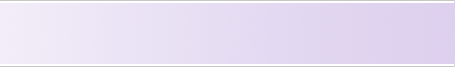|
第二百十七回: 基礎はつまらない
何でも基礎はつまらない、どうしてこんな事を繰り返しやるのだろうと思う。私も若い時、思った。
着たくもないYシャツにスーツ、締めたくもないネクタイ。 お客様に笑顔でハキハキと元気よく「いらっしゃいませ」って・・・全然できなかった。人材開発担当の教官から目を付けられ、ずっと叱られていた。しかし、それもできるようになるから、人間は不思議だ。図々しいもので出来るようになると、できない人を気の毒に思う。基礎ができないまま、本業に就いている人は苦労する事が多いようだ。
先日、とあるホテルに支払へ行った。生憎、請求書を持って行かなかった。フロント係から「請求書はないのですか? では開催日付と主催名をどうぞ。また、今後は銀行振込でお願いします」と一方的に言われた。一緒にいた人が
「ここのホテルは、いつからこんな対応になったのですか」と私に尋ねた。上下関係があるとは思わないが、200万以上の支払に行ったので少々面食らった。期日に遅れた納税者の気分だった。ホテルの宴会場、百貨店の特選売場は「上質な時間」を売っている。その空気の源は接客だ。いつも笑顔で、話しやすい雰囲気は誰にでも出せるものではない。しかし接客の基礎を積めは、人並みの接客はできるようになる。写真学科を卒業した頃の私は、無口だった(嘘だ!と言わないで下さい)。
「人見知り、拶挨できない、会話は弾まない」の三拍子だった。上記のフロント係の接客をとやかく言えない。聞かれる事と言えば「公衆電話の場所、化粧室の場所、連絡通路へのアクセス」の3つだった。駄目な私でも2年間勤めたので、佇まいというか百貨店員の姿になっていたのだと思う。髙島屋での活け込みで何度社員に間違われたか。「おはようございます」の一言でも、気持ちのこもった声は、人の心に響く。スポーツでもそうだ。野球の素振り、柔道の受け身、相撲の四股、サッカーのリフティング、基礎は見ていてもつまらないのだから、やっている方はもっとつまらないだろう。アナウンサーや声優の発声練習、美術部のデッサン、ピアノのバイエル、書道の楷書、楽しい訳がない。
それでも代々、そこから始めるのは、基礎に意味があるからだ。必要な物が多く含まれてい るからだ。基礎を通った者にしか理解できない段階がある。自身が素人だと思い知ることで慎重に行動する。何か見落していないか、一流と言われる人と自身との差は何だ、それを埋めるには、何を補えば良いか。上達への扉を開けてくれるのが基礎である。
いけばなも、鋏の握り方、枝の切り方、剣山へのさし方、水揚げの仕方。様々な準備と片付けが出来るようになって、始めて花の型や花材の組み合わせのレベルに移行する。
私は新しい花材でお稽古することを許されなかった。両親や生徒様の切り残した枝物や草花で活けた。真新しい花材でお稽古している生徒様に、内心「負けるものか」と思いながら一枝一花を挿していた。
どんなに遠くても、時間がかかっても、一歩一歩踏みしめて基礎を固めていくのが、先代の教えだ。
近道をすることを嫌った。大きな力に阿り、一足飛びに立場が上ってしまうと、強みも弱みも理解できないでいる危険を知っていたのだと思う。若い時はまだるっこしい作業が苦手だった私も、還暦近くになって先代に感謝している。
|