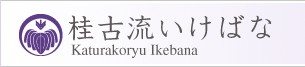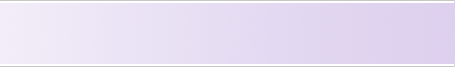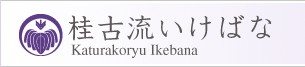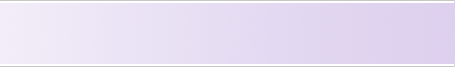第百九十七回: 庵號
桂古流では師範を取得すると庵號が付く。庵(いおり)とは小さな建物を指す。かつては華道師範ともなれば庵の一軒をも構え、華道に精進するとされた。庵を立てるにあたり家元に名前をお願いしたのが庵號の始まりだ。
いけばなという文化はそれだけ風雅を楽しむもので、現代からは浮世離れしている覚悟を持った人々が極めるものだった。仮に現在華道師範を持っている人が全員庵を建てると凄いことになると想像してしまう。住宅メーカーも庵シリーズを強化するかもしれないし、旅行会社は訪日外国人向けに庵でいけばな体験ツアーという企画をたてるかもしれない。
桂古流家元は汲雪庵である。字も音の響きも美しいし、お淑やかな印象を受ける。私はランニングが趣味で終始ドタバタ動き回っているから相応しくない。雪を汲み溶かした清水で花を活ける、眼を閉じてそんな姿を想像すると歌舞伎役者がお似合いだ。この「きゅうせつあん」という音、特に雪という優しくはかなげな一文字が私には解せなかった。浦和に雪が降らない訳ではないが汲むほどの量かと問われれば私の記憶にもない。比較的温暖で住みやすい所である。では雪はどこに由来するのか。
先日、サグラダ・ファミリアの主任彫刻家、外尾悦郎氏のドキュメントが放送された。世界で活躍し日本を発信する日本人とされる。私が大学生の時にアントニオ・ガウディ「聖家族教会」の展覧会が開催された。見に行った時の驚きは今でも忘れられない。様々な技法、知識、様式が集約されながら統一感のある建築物。揺るぎない美。静謐の中に豊饒な声があった。写真学科の恩師で後に主任教授にもなった原直久先生にその感動を伝えたら、一緒に喜んで下さった。
外尾悦郎氏に話を戻す。主任彫刻家である彼はイエスの塔に携わる。彫刻だけでなくステンドグラスの色にも拘っていく。日本人の外尾氏がなぜ1978年から長きに渡ってサグラダ・ファミリアの彫刻に関わることができたのか。氏は「ガウディを見ていたのでは答えは出ない。ガウディのやりたかった事は何だったかという事を考える。ガウディの立っていた所に立つ」と言う。この言葉が出るからこそ、外尾氏は後継の継続性と創造性を兼ね備えた人物として全幅の信頼を寄せられたのだろう。
ではガウディのやりたかった事とは何だろう。曖昧模糊として形があるような、掴み切れないような存在に思える。もしかしたら世阿弥が能を花に例えたように、ガウディの目指したものは雪だったのではないかとふと頭に浮かんだ。この世に居ないから今更聞けないし、たとえ聞いたとしても理解できるとは限らない。しかし先人に思いを馳せ、その考えに自らを添わせていく時、手のひらに載った雪のように淡く形の遺す一瞬がある。ガウディと外尾氏は勿論だが、私が歴代家元の資料や言葉を思い出す時、必死に活けている時「こういうことか!」と天啓に導かれる瞬間に「雪」が思い浮かぶ。それを何とか形にしよう、言葉にしようとする行為が「汲む」なのではないか。
ガウディの建築資料が戦災でほとんど無くなり人々の口づてに再開されたように、いけばなも先代から当代に伝わる事は決して多くはない。時代に合わせるため大胆な変化も必要となる。汲雪庵とは歴代家元の声なき声に耳を傾けつつ、その時代の最良の手段で実現する。その為の方策を模索する者にこそ相応しい庵號だと私に語りかけているようだ。
そしてバルセロナブルーの空にそびえる巨塔群は、完成を目指し姿を少しずつ変えていく。今日もそしてこれからも。
|