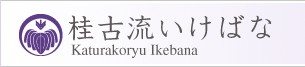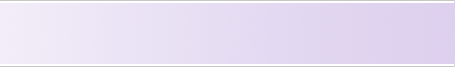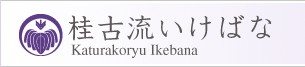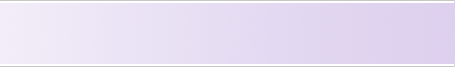第百九十八回:
花器を求めて
平成初期の桂古流展での話から今回はスタートする。花展直前に桂古流では恒例の花器販売会を家元本部で行う。「展覧会だから良い花器が欲しい」という生徒様のご要望に応え、取引先の茶華道具店に数日花器を展示販売してもらう。
ある時、社長から花器を仕入れに行くのに同行して欲しいと頼まれた。その道具店は社長が茶道、奥様が華道を主に取り扱っていた。奥様が体調を崩し、その間社長が花器の買い付けも兼ねることとなった。茶道で陶磁器を見る眼は自信があり、花器の選別もできると思ったのだろう。買い付けてきた花器が店頭に届き意気揚々と見せると、番頭さんに「よくこれだけ売れそうにない花器ばかり買い付けてきましたね」と厳しい一言を返される。しょげた社長が販売会を前に私達と一緒に窯元を回り、私達が求める花器と同じデザインの花器や似ているもの色違いものを仕入れるという案を思いついた。
普段行く事のない窯元で、直に製造工程や大量の花器が見られるので、貴重な経験をした。
当日、新幹線で名古屋へ向かった。名鉄に乗り換え常滑へ。急須や招き猫の印象が強いが花器の一大生産地であった。まずは光山焼を見に行った。朱泥のイメージが強いが、白い花器も美しかった。現在も使っているコンポート花器はシンプルなデザインで人気がある。光山焼では茶道具の菓子器も興味深かった。茄子型の菓子器を買った。続いて秘色に行った。秘色は私の華道歴にいつも側にあった。自身の稽古も秘色、師範の課題花器も秘色、気に入った水盤も秘色だった。秘色焼製陶所(秘色窯業)は宝石箱のようだった。発色の豊富さ、使い勝手の良さは群を抜いていた。閉鎖してしまったのが本当に悔やまれる。ここでもいくつか花器を求めた。
この旅のすごい点は、私たちをリレーのように次の生産地へ移動してくれることだ。朝食を済ませ、常滑の業者様の車に乗せてもらった。三重県の四日市辺りだったのだろうか、次の生産地の方が既に車で待っていてくれた。信楽焼の方だった。たぬきで有名な印象だが、花器のバリエーションが豊かだ。一軒目はかぶと焼といった。山道の納屋というか物置のような中に案内された。恐る恐る入ると整然とラックに花器が陳列されていた。外見と内部がこんなに違うのも珍しい。特に印象強かったのは、緑と茶の縦縞の花器だ。2個買った。60~70cmくらいの高さで派手過ぎるかと思ったが、どんな花材でも相性が良かった。時間が限られているので急いで選んだ。入る時は躊躇っていた納屋は帰るのが残念なほど素敵な場所に変わった。続いて信楽焼の第一人者、楽入氏の窯元へ行った。今までの商業花器とは一線を画す佇まいだ。氏は温厚な眼差しだが風格のある人物だった。信楽焼は草(カジュアル)の花器なので真(フォーマル)の床に活ける事はない。が、格式を超えた威厳が楽入氏の壺にはあった。壺の肩は丸味を帯びている。灰かぶりの部分は力強く二つと同じ物はなかった。
この後、信楽焼の業者の方が車で大津辺りまで送ってくれた。今度は清水焼の業者さんが迎えに来てくれた。
清水焼(京焼)は一口に「これ」と言い切れる特徴は表現しづらい。全体を見ていると都らしさがしっかり感じ取れる。色の取り合わせ、質感、手ざわりを通して花器が私に「清水焼とかこういうものだ」と教えてくれているようだ。三浦伊六、長谷中和夫、尾川稔は京焼の中でも花器作りの専門家だった。この時は奥山華善、市川博一を求めた。
社長は各生産地で私たちが気に入ったり手に取った器を、その場で買い付けていた。
お互いの目標を達成した時は一日が終わろうとしていた。夕食はどこかで食べたのだろうし、新幹線に乗って帰って来たのだろうけれど記憶に残っていない。花器買付弾丸ツアーはひたすら花器を選び続けていた事のみを忘れられずに残っている。
|