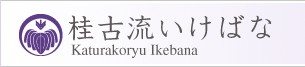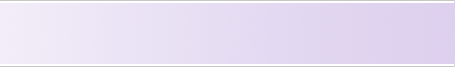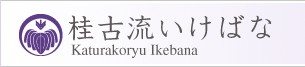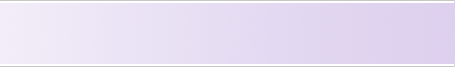第百九十九回:
土俵
仕事をする時に相手の土俵にあがっていく場合もあれば、こちらの土俵で進めることもある。
社会人の前、学生時代から「これはどちらの土俵か」というのが気になる性質だった。マークシートや穴埋め問題は当てはまらないが、記述式や論文での回答を求められる時「これは出題者は何と答えさせようとしているのか」「どう答えて欲しいのか」を考えてしまう。そういう指導を受けたのかもしれないが、自身の中で相手の立場に立って考える癖があり、試験でもその様な解答をしてしまう。
例えば論文のテーマで「あなたの求める未来」について記せ、と出題されたとする。私はそれをそのまま受け取らない。仮にそのまま受け取ったら「働かないでも一生暮らしていける人生」などと舐め切った事を書いてしまう。論文を書くことになった志望する企業・学校にうかるため、出題者に気に入ってもらうための文章を書くことが大切になる。こちらは貴方が求める人物ですとアピールする手段として文章を書くとなると、自身と離れた「あなたの求める未来」になっても仕方ない。
この様な時は相手の土俵に上がることになる。相手の土俵に上がるには相手の規則やしきたりがある。そういう枠をとらえて素直に従えばいい。元気のある人を求めているのか、仲間との協調性を大事にする人を探しているのか、海外で働きたい人に興味があるのか。相手側の情報を先にリサーチしておけば内容を絞り込むのは比較的容易になる。同程度の文章でも採点者への好感度は大事になる。
遊びに於いても相手の土俵にあがる場合がある。日本いけばな芸術特別企画in金沢を開催するにあたり、21世紀美術館とその付属施設を見学に行った。決められた時間内に花展会場、デモンストレーション会場、講演会のホール、体験スペースなどを確認し、こちらの条件と擦り合わせた。初めての会場で開催する展覧会が上手くいくか、どんなトラブルが予想されるか、それを防ぐにはどのような対策が必要かを想定しながら見ていくのは疲労する。
夜は金沢に詳しい先生がひがし茶屋街に連れて行ってくれた。今のように外国人観光客目当てのお店になる前、芸妓さんにお座敷遊びを教わった。有名な「とらとら」というものだ。座敷に衝立を立て隣が見えないようにする。歌に合わせて3つのうち何かのポーズをとる。虎か、武者か、その母親の3つだ。武者は虎より強く母親は武者より強く、虎は母親より強い。ジェスチャーのじゃんけんのようになっている。歌を歌っている間に、槍を突く姿(武者)、背中を曲げて杖をついている姿、四つん這いの姿を選ぶ。衝立の反対側で相手が何になるか考えなくてはならない。こういう遊びは初めてなので素直に相手の土俵にあがる。勝っても負けても構わない。アハアハ笑ってその場の空気を愉しめばよい。
相手の土俵に上がることもあれば、こちらの土俵にのせる事もある。電話やインターネットの商品案内の方には、APEXは再開発地域で集合住宅扱いなので管理組合にお問合せ願いたい旨を伝える。学院の設備や資産運用に関しては財団法人の理事会で議決する案件なので、私の裁量を超えているとお応えする。私の立場をお伝えすることでご納得頂けるとありがたい。
いけばなも土俵がある。相手の土俵に上がる時はご迷惑が掛からないよう細心の注意をはらう。場所、時間、人、予算と様々な要因を想定する。相手が求めているいけばなは、私のどの部分か。お話しできる所か、古典花の技術か、活け手の外見か(それはない)。準備の段階ではそれらを一つずつクリアにするため神経をつかう。準備は相撲と同じで色々手順がある。私が打合せ、発注、現場の下見を粛々とこなすのは、相撲の取り組みまで土俵で四股を踏み、塩を撒くのと同じだ。土俵で制限時間いっぱいとなり軍配が返るとそこは戦いの場となる。礼儀や威厳を吹き飛ばし勝つことに集中する。いけばなも活ける!となった瞬間周りに見えていた物、話していた人は感じなくなる。ただ花を活ける、その事だけに全精力を注ぎこむ。
|