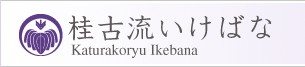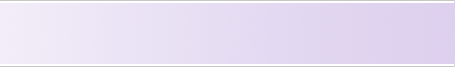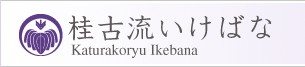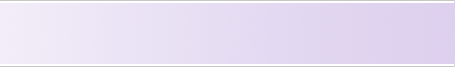第二百五回:
興奮をどう形にするか
次男の玉兎は総合格闘技を友人と観戦するのを楽しみにしている。コロナ禍によりYouTubeでしか応援できない時期もあったがここの処でやっと直接会場に行くことができるようになった。試合後のインタビューでも選手からのメッセージは「ぜひ会場に見に来てください」というものだった。次男がコロナ禍で痛感したのは本物の興奮だ。会場でしか伝わらない音とか飛び散る汗とかがSNSだと伝えきれない。SNSはもちろん便利なんだけれどデータのすき間からこぼれ落ちてしまう物を感じると。玉兎は平成生まれ令和に青春を謳歌している者がそういう発想になるのだなあと感慨深かった。玉兎は「いけばなもそう思うんだよね」と語った。「SNS万能の時代で作品を公開、発信できたりする。それはそれで良いのだけれど、展覧会にいって花の匂いとか、会場と作品の調和から生まれる空気感など足を運ばないと得られない興奮がある」と。
便利な事と興奮は一致しないこともある。不便ゆえに得られる興奮もある。目の前に広がる風景、私にとっては自動車や電車より自転車そして自身の脚と体力を必要とする方が、細かい部分まで楽しめる気がする。花の時期が過ぎ、実がなり始める街路樹や、公園の刈られた雑草のあとに、草が少しずつ伸びている様は実際の風景との距離感が大事だと思う。緻密に眺めるならば自らの脚に頼むのが一番だ。
辞書を引くことも大きな出会いにつながる。漢和辞典には画数、意味、用例、出典が国語辞典には意味が列挙してある。隣から隣へよそ見して調べたい項目以外も目に入る。余計なことまで頭に残る。GoogleやYahoo!などの検索サービスは便利だ。初めに使った時「何てすごいシステムができたんだ。これで暗記の苦手な私も恥ずかしい思いをすることが減る」と感激した。しかしこのシステムを多用すると知識の振れ幅は少なくなるだろうとも感じた。皆が画一的な知識・思考回路になってしまう危惧も覚えた。点でしか出てこない正解の怖さ。自分の意見ではない模範回答のみ横行する不気味さ。大量生産のような論文は人間が求めていたものなのか。
高校の時に倫理の授業で「一冊の本を読んで感想を書け」という荒っぽい宿題がでた。55人中提出したのは2人。まったくひどいクラスである。友人は大江健三郎について。私は土光敏夫の「日本への直言」を読んだ。倫理に関係ないとは思ったが祖父に似た生き方をしているので驚いた。目刺しを食べる土光と時間を惜しんで豚汁を赤飯にかけて慌ててかき込み教場に戻る祖父が重なった。2つしかないレポートに嘆きながら倫理の先生は高評価をくれた。倫理の先生の推薦書籍でなくて良かったのかと40年経った今でも思う。
知識を得る興奮はさらに研究意欲をかきたてる。私は研究会の時に板書や朗読を取り込む。人の温もりが希薄な授業は興奮を呼ばない。いけばなのお稽古に来てくれるのだから、桂古流に出合えた喜びを教室で味わってもらいたい。私自身にできる事は何か問うと、朗読の声やホワイトボードの肉筆から温もりを伝える事ではないかと帰結する。ささやかだけれど確かな興奮を届ける工夫こそ指導者の腕の見せどころだ。
スポーツにしろ芸術文化にしろ実際に経験した人ならば画像からも理解できるだろう。
六世華盛、七世華慶の作品にある色気の正体は、今になって思えば立活けの重厚さを軸にしながら軽味の魅力があった。肩の力をスッと抜いたような枝の流れ、何でもない簡単そうに見える自然な佇まい。どれだけ努力すれば到達するのだろう。歴代の作品写真を見るたび実物はどれほど美しかったのだろうと興奮してしまう。
|